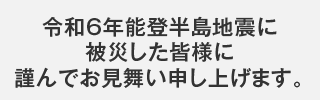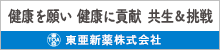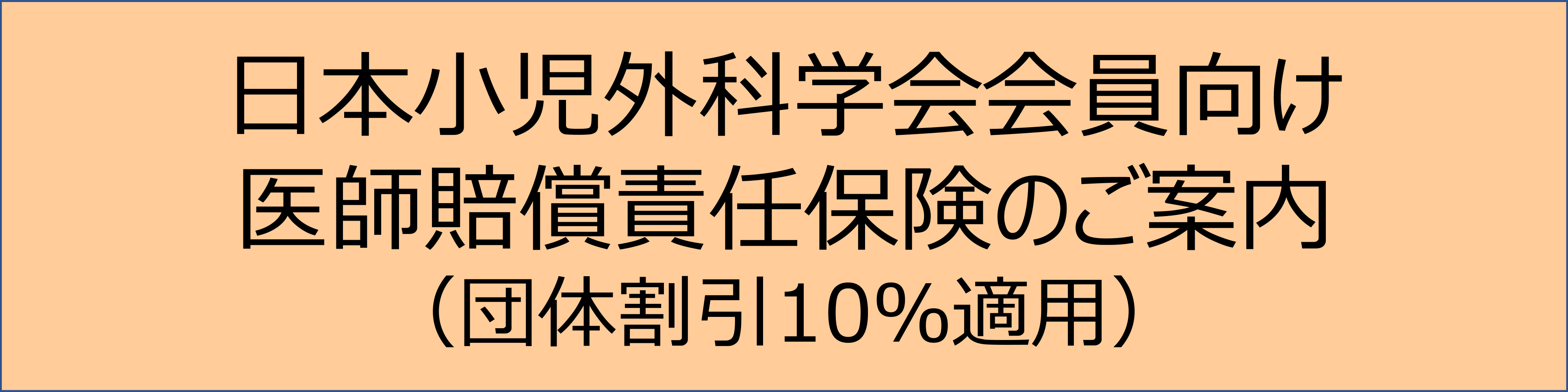連 利博(日本小児外科学会会員 茨城県立こども病院)
私は40才代後半、兵庫県立こども病院で小児外科スタッフとして勤務していた頃に、ひょんなことから途上国の小児外科医療支援に携わることになった。事の発端はネパールから留学していた神戸大学小児科大学院生P医師が兵庫県立こども病院小児外科にローテートして来たことに始まる。P医師は日本の某医療救援NGOのネパール支部のメンバーであり、英語で私と十分なコミュニケーションができたのでいろんな話を聞かされた。彼はネパールの医療過疎地域に小児病院を建てるという夢を持っていた。当時、ネパールには首都カトマンズにトリューバン大学関連のカンティ小児病院があるのみで、地方の子どもたちに医療が必要なときには親が野を越え山を越え、2,3日がかりで連れてくる状況であった。
途上国支援といっても何をすればよいのかイメージし難く、まずはその国の医療レベルを示す指標が必要である。UNICEFが毎年出す統計データの中で5歳未満児死亡率(U5IMR)は一国の医療レベルを示す指標とされている。ちなみに、当時(2002年)この死亡率の最も高い国はシオラレオーネで1000出生中316人で、ネパールは当時1000出生中100人であった。一方日本はすでに4人に到達していた。ちなみに、2013年現在のネパールでは40人と半分以下になっている。(http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT)
P医師は在日中に毎日新聞大阪本社の協力をとりつけ、新聞社はキャンペーンを通じて見事に浄財を集めた。この間に阪神淡路大震災が起こったが、そのことも相互扶助の精神に拍車を掛けた。彼は病院をインドとの国境付近で、ネパールの東西南北の幹線道路が交差するところにある町、ブトワールを建設地と定めた。毎日新聞社会事業団が病院建設を担当し、世界的な建築家、安藤忠雄氏がボランティアで設計してくださり、運営を某NGOに委託した。某NGOは元来緊急支援のNGOであり、小児病院の医療技術のレベル向上と維持ができる専門員はいなかったのでその役目を私に託された。光栄なことであったが、私の年齢で私自身が途上国支援に身を置くことはプロフェショナルとしての岐路に立つわけである。自分としてはアカデミックな課題を持っていたので、途上国支援を本格的にやるという決心は容易ではなかった。そこで私はまずは現地をこの目で見ようと、彼と毎日新聞大阪本社担当の新聞記者とで現地視察に行った。

村の人々は花束で私たちを歓迎してくださり、子ども達の輝く目は今もまざまざと私の脳裏に刻まれている。
10人に1人の子どもが亡くなっていく世界で生きている子ども達の目はむしろこれほど生き生きとしているのだと感動した。悩んだあげく私が考えたのは、「私の身分、すなわち地方公務員の勤務医としては、現地に行けるのはせいぜい年に1度だけ、同僚の好意にあまえ1週間程度の休暇をもらってネパールに行くしかない。現地にはP医師もいるのだし、私にとって二者択一でない範囲ならやってみよう」ということであった。せっかくの機会であり、未知の世界を見たいという好奇心で承諾した。実際には私の小児外科医としての人生に何らかの影響を与えたように思うが、特に後悔しているわけではない。

病院が建設されオープンしたのは2年後の1998年であった。その2年間に、私自身は先ずはその国の小児外科のトップレベルを知らねばと考え、唯一小児外科医のいるカンティ小児病院に1年に1度、合計2回訪問し、外科のレベルをつぶさに観察し手術指導もさせていただいた。
また、現地で遭遇した優秀な研修医、M医師を兵庫県の海外交流資金で8ヵ月間招聘し兵庫県立こども病院で小児外科トレーニングを行った。自立を目指した支援であるからには、人材育成は重要な課題であった。少々、我田引水になるかもしれないが、小児病院というのは一般に外科系の治療ができなければならない、それが小児病院の小児病院たる所以だと私は思っている。小児病院には、新生児の手術、先天異常の再建や小児悪性腫瘍摘出など外科的疾患をその臓器機能を温存した再建ができる外科医の存在が必要である。途上国では腸炎や肺炎などの感染症の患者が多くそれらの治療が大半を占めるが、それは一般病院でも内科医によって可能な治療である。
1998年秋、病院はブトワールに「シッダルダ母と子の病院」という名前でオープンした。

この地はタライ平野にあり、お釈迦様の誕生の地、ルンビニに近い。シッダルダは釈迦の幼少期の名前である。その場所は、都会の喧騒の中で生まれ育った私にとっては静謐で時空を超えた特殊なところであった。院長となったP医師は、ネパールは女性の地位が低く、実際受療機会も少ないので、この病院を女性に配慮した病院にしたいという気持ちを込めて命名したそうである。シッダルダを生んだマヤ・デヴィも産褥熱で亡くなったと聞いた。翌年には産科がオープンし、その地域で唯一の帝王切開のできる病院となった。
われわれはオープン後の2000年の訪問時に6例の本格的な小児外科手術を行った。特筆すべきは、首都から遠く離れた町で生後16日目の体重2.5Kgのベビーの臍帯ヘルニアの手術と2ヶ月のベビーのヒルシュスプルング病の手術に成功したことである。前者のベビーはこの病院で誕生し、同病院で手術を受けたという文字通りの周産期の一貫した治療を享受したわけだ。イギリスで教育を受けた麻酔科医がいたので可能となった。手術は同伴した日本人小児外科認定医(現長崎大学の大畠雅之先生)、8ヶ月間日本でトレーニングを受けた現地M医師と手術室勤務の日本人看護師と私であたった。現地に呼吸器はないが、気管内チューブはすぐに抜けると判断して臍帯ヘルニア手術を行ったのであるが、術後自発呼吸が不十分で日本から同行した麻酔科医が挿管のままでバギングしてくださり、夜中に抜管に持ち込んでくださった。術後は現地のM医師に任せて帰国したが、術後管理のサポートはメール通信で可能であった。人材さえ確保できればネパールでも新生児手術がある程度可能であることがわかった。
途上国において小児外科をどこまでやれるかは、呼吸器が使えるかどうかに依存しているように思われる。横道にそれるが、例えば小児外科疾患の中で食道閉鎖症の治療成績は一国の小児外科レベルを表すと言われている。日本と対比して考えると、第1回日本小児外科学会総会が開催された1964年の食道閉鎖症の死亡率は60%であった。その頃のわが国の乳児死亡率はすでに1000人に対して30人であった。乳児死亡率とU5IMRとは一致しないが近似値とすれば、現在のネパールがそれに近いものと想像する。ちなみに、日本小児外科学会が最近支援をしているカンボディアのU5IMRは2013年で38である。カンボディアでの小児外科は人工呼吸器のサポートの必要な外科疾患を解決することで飛躍するだろうと推察する。
シッダルダ母と子の病院は診療代や入院費を現地の公立病院並みに設定し、彼らの献身的な活躍で地元の村民たちに支えられたすばらしい病院に発展した。私はこのようにして一つのNGOに参加して、中古の医療機器集めや仲間達と資金集めにも励みつつ途上国支援を体験し、5年契約の支援は一応完了した。
しかし、いいことばかりでもなかった。途上国では肺炎で死ぬことも多いが、途上国においては人工呼吸器の数は限られているだろうから肺炎などの呼吸不全に長期使用するのは難しいかもしれないなどと考えさせられた事例も経験した。過渡期においては臍帯ヘルニア術後など術後一晩だとか短期使用で終わることが可能な場合にむしろ適応があるのかもしれない。このようなことを体験しながら、ボランティア契約した5年間が過ぎようとする頃から私は訪問する頻度を減らした。メールでリアルタイムに情報が直接行き来する時代である。いろんな情報が入ってきたが、病院の自立とともに、某NGOの日本本部とネパール支部の思惑など様々な利害が交錯したようであるが、メールだけで日本にいたままでは私には真実はわからない。ここで初めて本当の二者択一を迫られたのかもしれない。私はその地域の医療に貢献するために自分の身を現地においてまでできるかと言えばNOであった。日本にもまだ克服できていない病気があり苦しんでいる子どもたちがいて、私にとってはやらねばならない研究テーマがあった。途上国の村の人たちの目線を体験しつつ、この時期かなりのエネルギーをこれに費やした。今まで知らなかった世界の人たちとの交流もでき、非日常的な貴重な経験であったことは事実である。私は途上国の小児外科医を一人育てたのでなんらかの貢献はできたと思いたいが、好奇心で国際援助に参加したということは自己満足のために参加したということになり、現地の人から見れば私の途上国支援は中途半端であったろうと思う。現地の人たちを最後までサポートできなかったことに「申し訳ない」という思いもあることを皆さんにお伝えして、この話を終えたい。
途上国支援に興味ある若き小児外科医の参考になれば幸いである。